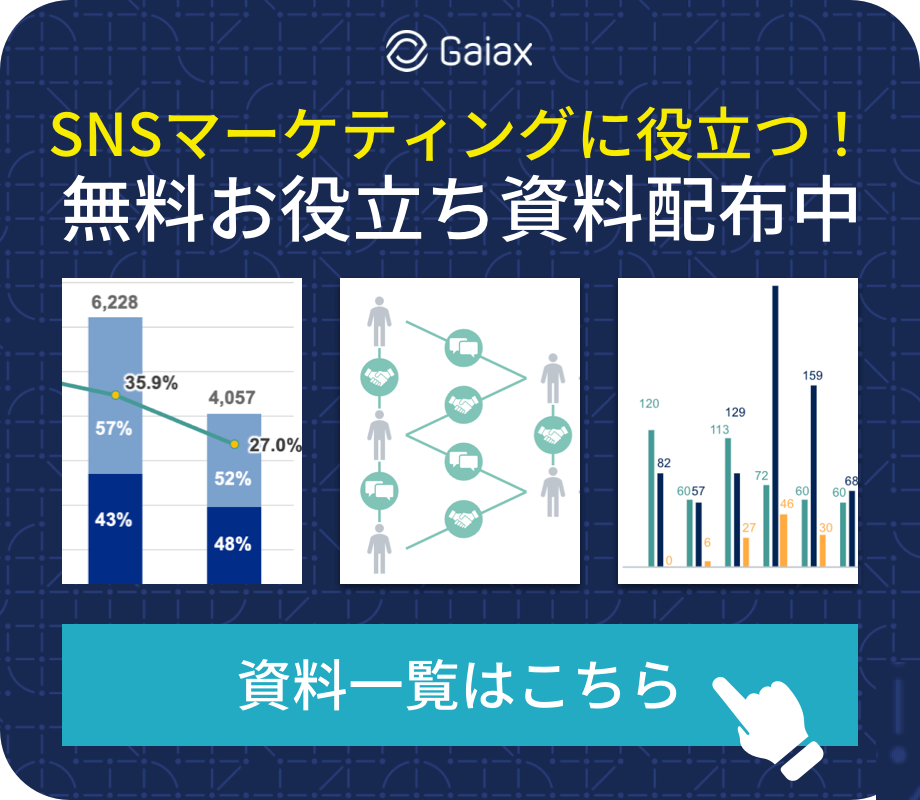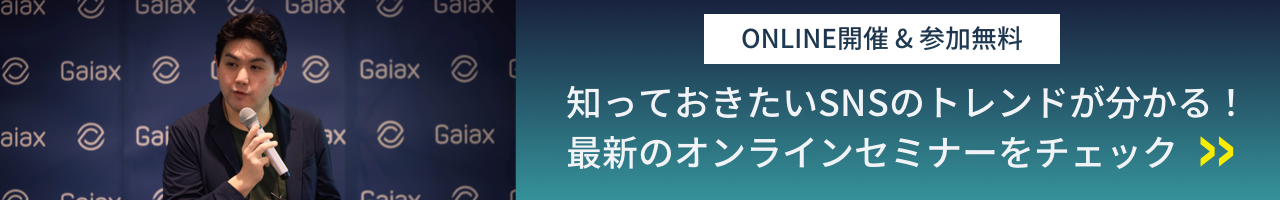「スタンプに代わるものを」、LINEスポンサードエフェクトが目指す新しい広告のかたち
2018/02/19

2017年12月より、イタリアブランドのFENDIや、ECサイト最大手の楽天市場が提供しはじめたことなどで話題を呼んだ、LINE「スポンサードエフェクト」。
ユーザーの顔や表情を認識し、コミュニケーションを行うことができるビデオ通話や、トークルームカメラにおけるエフェクト機能を活用したこの新しい広告サービスは、どのような経緯で誕生したのでしょうか。また、どのような点で差別化を図っているのでしょうか。LINE株式会社執行役員、広告戦略担当の葉村真樹氏に伺いました。
Interview / ソーシャルメディアラボ編集長 大久保亮佑
Text / ソーシャルメディアラボ副編集長 小東真人
- ■目次
- プロフィール
- LINEの新広告メニュー「スポンサードエフェクト」とは
- 「スタンプに代わるもの」を提供したかった
- 他のプラットフォームでの拡散も見込める広告
- ユーザーの日常に溶け込んでいる広告
- 今後の展望
1. プロフィール
葉村真樹 氏:LINE株式会社 執行役員 LINE Ad Business センター

2. LINE新広告メニュー「スポンサードエフェクト」とは
ユーザーの利用場面は3つ
大久保:スポンサードエフェクトとはどのような広告なのでしょうか?
葉村氏(以下、敬称略):スポンサードエフェクトは、使える場面がおもに3つあります。 一つは「ビデオ通話・グループビデオ通話機能」二つ目はLINEトークルーム内から起動できる「トークルームカメラ」さらに三つ目は、昨年の8月中旬にアップデートされた「チャットライブ」です。チャットライブとは、特定のトークやグループ内でライブ配信ができるサービスを指します。身内のみに公開するなど、クローズドで利用できるところが特徴です。
一つは「ビデオ通話・グループビデオ通話機能」二つ目はLINEトークルーム内から起動できる「トークルームカメラ」さらに三つ目は、昨年の8月中旬にアップデートされた「チャットライブ」です。チャットライブとは、特定のトークやグループ内でライブ配信ができるサービスを指します。身内のみに公開するなど、クローズドで利用できるところが特徴です。
これら3つの機能において横断的に使える「エフェクト」を広告として展開したく、昨年末から販売を行っています。また、カメラ上でエフェクトを起動して撮影した静止画・gif画像、動画は保存でき、ほかのSNSアプリでそれらの動画をシェアすることもできます。
顔認証が面白い

大久保:保存もできるんですね。エフェクトには具体的にどういった種類がありますか?
葉村:ユーザーの顔を認識する機能があり、それに対応したエフェクトがあります。たとえば「口を開けてください」「瞬きしてください」というようなメッセージを設定でき、メッセージの指示に付随したユーザーのアクションを引き出すことができます。
大久保:今の時点でどのくらい使われているのでしょうか?
葉村:エフェクトは、現時点で月間平均6000万回以上使われています。カメラは400万DAU、700から800万回の起動回数です。ユーザーさんに使われている場面もかなり増えてきていると感じています。また、ビデオ通話の平均通話時間は「7分」と比較的長めです。
3. 「スタンプに代わるもの」を提供したかった
テキスト以外のコミュニケーション領域を
大久保:そもそもスポンサードエフェクトはどういった経緯で生まれたのでしょうか。
葉村:テキストやスタンプだけでなく、より「インタラクティブ」「ビジュアル」「リアルタイム」なコミュニケーションをやっていきたいと考えていました。したがって、スポンサードエフェクトは、この三つの要素を体現する機能、そして機能に付随する広告サービスという位置付けになります。
大久保:なぜビデオチャットといった「動画」なのでしょうか。
葉村:InstagramやX(Twitter)がすでに動画機能をつけているのは背景にあります。さらに、この背景の手前になるかもしれませんが、ネット環境がよくなり、Wi-fi経由や4GでLINE通話することが増え、ビデオ通話自体もすごく増えてきています。
しかし、いまだにLINEは「テキストとスタンプのみのやり取り」であるという固定概念も根強い。だから、動画インタラクティブの活用を通じて、「スタンプに代わるもの」でのコミュニケーションや付加価値を提供してみることになりました。結果的に、エフェクトはすでに月6000万回以上のペースで使っていただけています。
ビデオ通話の利用シーンについて
大久保:ちなみにそもそもビデオ通話と通常メッセージの利用シーンは、それぞれどういったものを想定していますか?
葉村:その質問は、ある意味「ビデオ会議とメールとの違いは何ですか?」ということと似ているとおもいます。従来のテキストベースでのコミュニケーションと、「リアルタイムで表情を見ながらなんでもない話をする」というコミュニケーションは、やはり性質もコミュニケーションの発生するシーンも異なりますよね。
ビデオ通話ですと、リアルタイムで行われますよね。人と人が同じ時間を共有して繋がることができます。たとえば、「恋人同士」や「おじいちゃん・おばあちゃんと孫」といったプライベートでの関係性が強い人たちに親しまれやすいのではないかと思います。一方で、従来のLINEのテキストコミュニケーションは、時間軸をずらしたやり取りに適切なのではないでしょうか。
4. 他のプラットフォームでの拡散も見込める広告
大久保:スポンサードエフェクトならではの、特徴について教えてください。
葉村:特徴の一つには、非公開チャットでの拡散も見込めるということですね。ここまでビデオを中心に話をしましたが、写真についてもお話すると、トークルームカメラで撮った写真自体をLINEのトークルームにシェアをする、タイムラインでシェアをする、あるいはグループに投稿する、という拡散もありますよね。

さらに、それをX(Twitter)やInstagramなどを通じて、ほかのソーシャルプラットフォームにシェアするという状況も生まれています。
大久保:一般公開ではないところでの、ユーザーの行動がどんどん追えなくなってきている中で、クローズド領域における拡散の仕組みを持っていると。
葉村:そうですね。ただ、この仕組みは要素の一つと考えています。あくまで、基本的には「LINEらしい」「LINEならでは」の体験でブランドを体験してもらうことを、全ての広告商材に共通して追求しています。
5. ユーザーの日常に溶け込んでいる広告

大久保:ユーザーがクリエイティブを楽しめるかどうかは大事だと思いますが、この広告メニューでもユーザーに好まれないものはLINEさんの方で断ったりするのでしょうか。
葉村:やはり、その点はすごく大切だと思います。ユーザーに好まれてこそ「リアルタイムでも発生しつつ、シェアもされる」という非常に能動的なアクションが巻き起こる。その火付け役となるクリエイティブにこそ、意味があると考えています。
たとえばクリスマスや年末年始を挟んでわかったこととして、その4週間の間、スタンプがかなり安定して使われていたということが挙げられます。また、特に冬休みやクリスマスイブの日に、カメラ機能での撮影がたくさんされていたり。大晦日や元旦の1月1日にも、ビデオ通話は伸びていました。
つまり、遠隔地間でも、リアルタイムで話せるというビデオ通話の強みが、数字に反映されていたのだと思います。要するに、ユーザーの生活に寄り添えるコンテンツそのものが、サービスになるべきなのだと思います。
大久保:「ユーザーの生活に寄り添える」、大事ですよね。
葉村:はい。たとえば冒頭で、スポンサードエフェクトにはユーザーの顔や表情を認識し、コミュニケーションを行うことができる機能があるとお話しましたよね。
この機能を広告と組み合わせるには、ユーザーが日々の生活のなかでどういうシチュエーションでどのような表情をするか、どのようなユーザーが、どのような表情を楽しむか、という点について考えなければいけません。
「口を開ける」「目をパチパチさせる」という動作でしたら、美容系やラグジュアリー・アクセサリー系の商品をつかう人が疑似使用する体験にからませることができるでしょう。飲食系の広告であれば、ガムを噛むフリをしたり(さらに「プー」するとガム風船が消えるというように)ユーザーが楽しめる「動き」と、打ち出したい商品とを掛け合わせた色々なクリエイティブのアイディアが出てきます。
こういう組み合わせをすることで、今までのような「見せられる」「配られる」「読まされる」といった受動的な広告ではなく、ユーザー自らが主体的に楽しんでもらうことによって、自然にブランドへの親近感や好感を上げていく。新しい広告の世界を切り拓くことができるのです。
広告業界では、一時期ネイティブアドという言葉も流行りましたが、やっぱり一番よいのは喜んで使ってもらえるものだなと思っています。
6. 今後の展望

大久保:では、最後に今後拡張していきたい機能や改善していきたい点など、これからの展望をお聞かせください。
葉村:LINE公式アカウントへの「友だち追加でダウンロードできる」という流れは、LINEが目指す広告のあり方や、方向性を、とても象徴的に示しているものの1つかなと思います。
つまり、広告自体がユーザーに対するサービスだと捉えています。だからこそ、広告主側にだけ使う価値があるような、単純に「自分のメッセージを伝えたい」というニーズを叶えるためのメディアではなく、ユーザーに対してなんらかの価値を提供するための、チャネルとして理解してもらえたら、と思っています。
ですから、あくまで「広告」サービスを提供した結果として、ユーザーのブランドに対する好感度が上がったり、購買意欲が湧いたり、という流れをつくりたいですね。従来マスメディアが配信してきたテレビ広告や、新聞・雑誌広告の延長線上ではない、新たな切り口から生まれる「広告」が求められる中、いろいろなことを仕掛けていきたいです。
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部